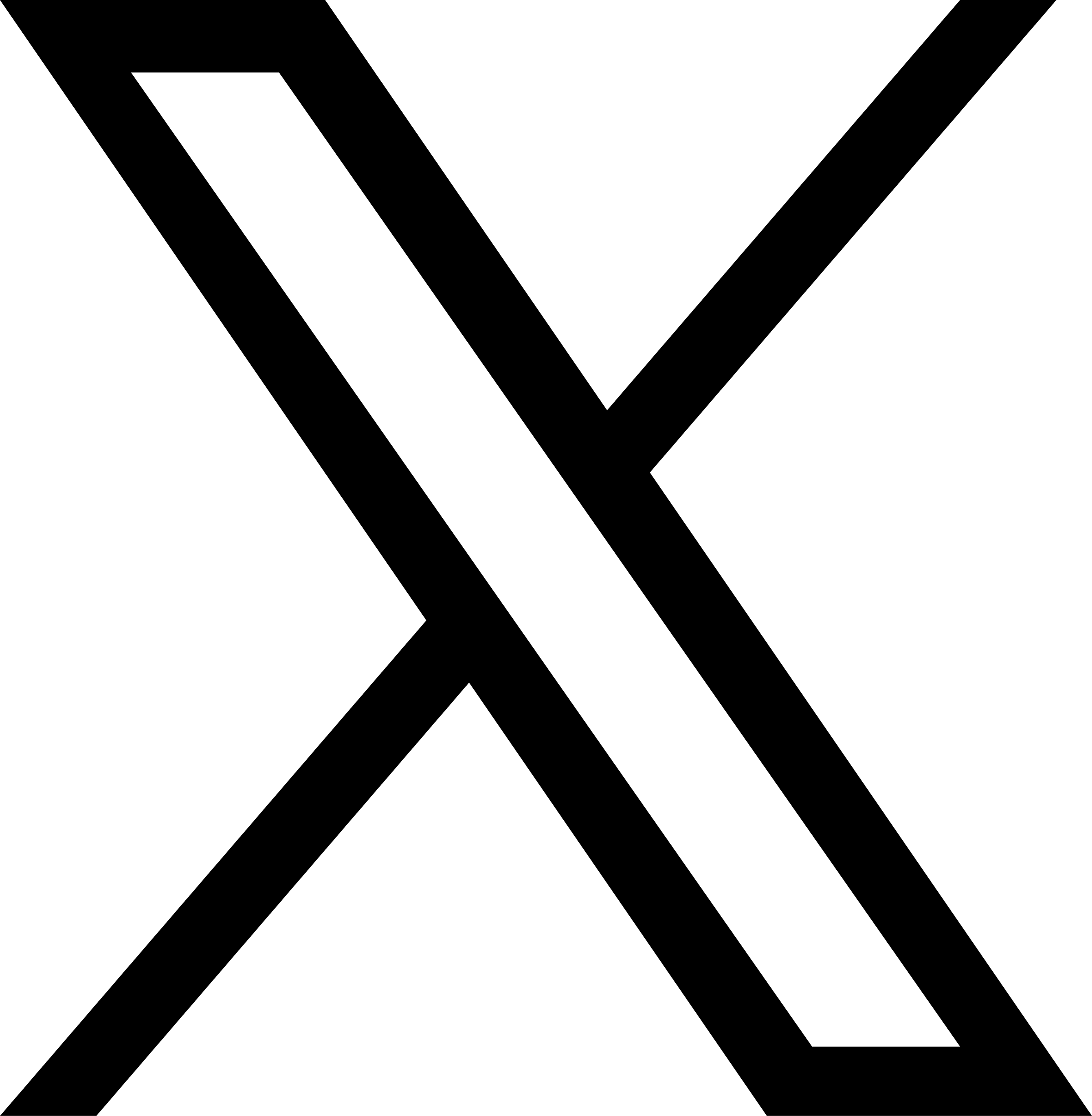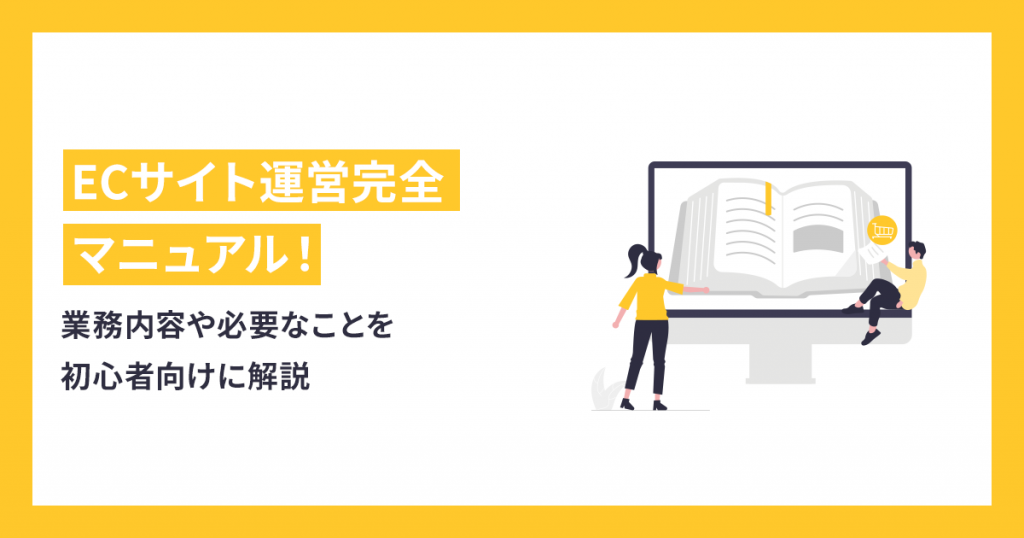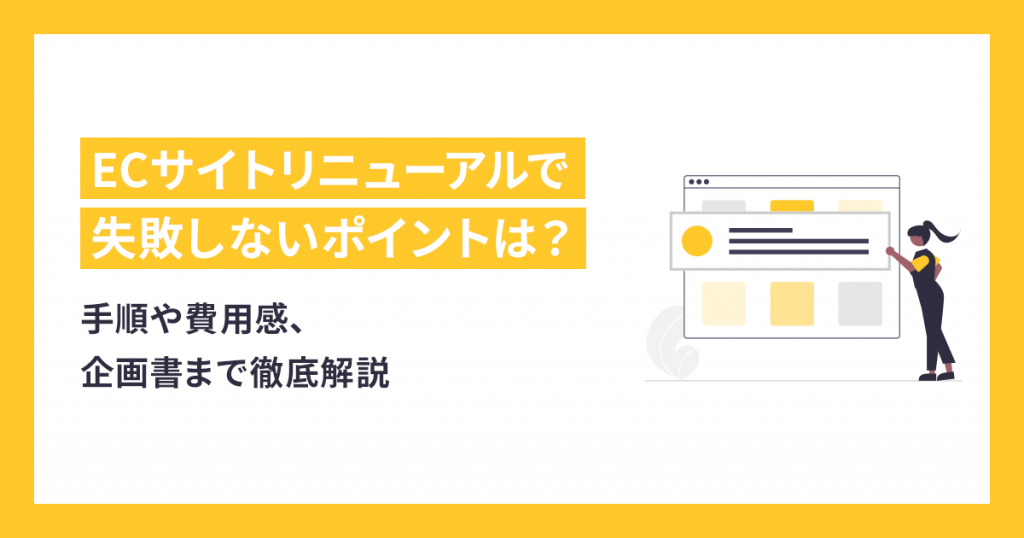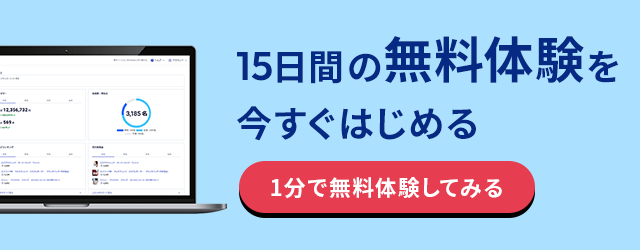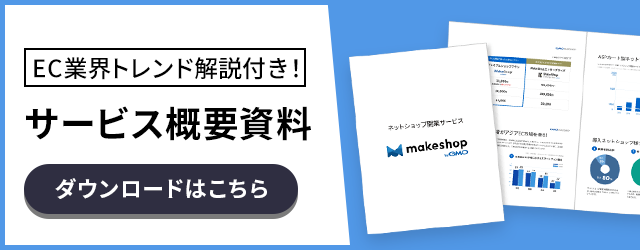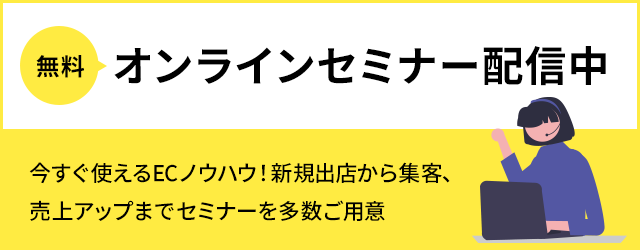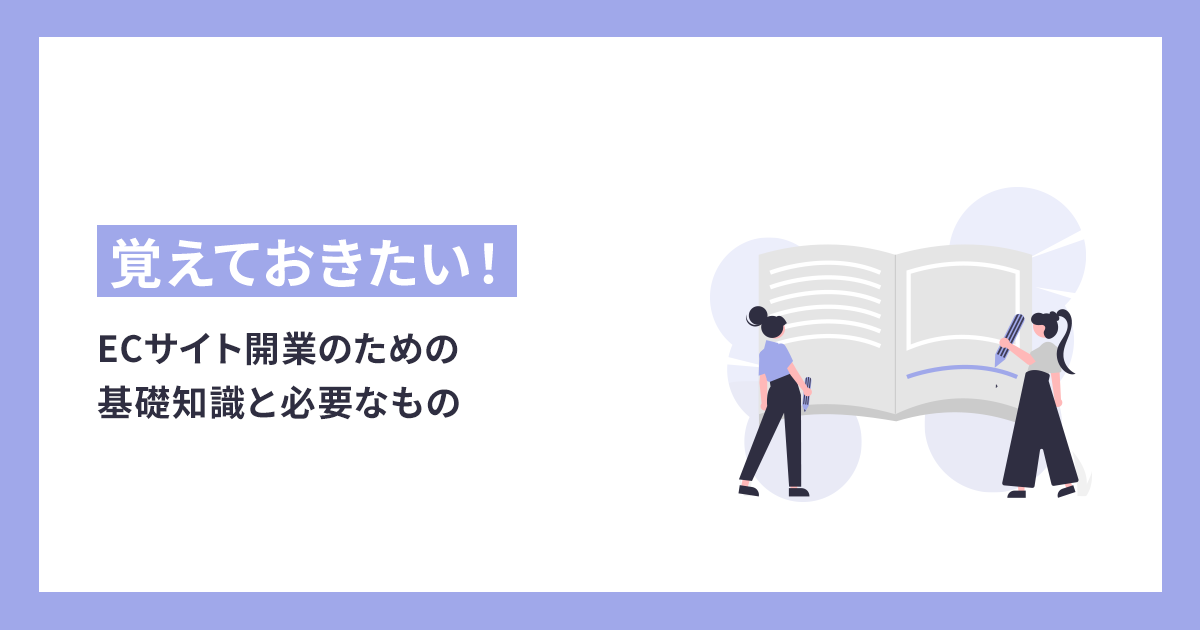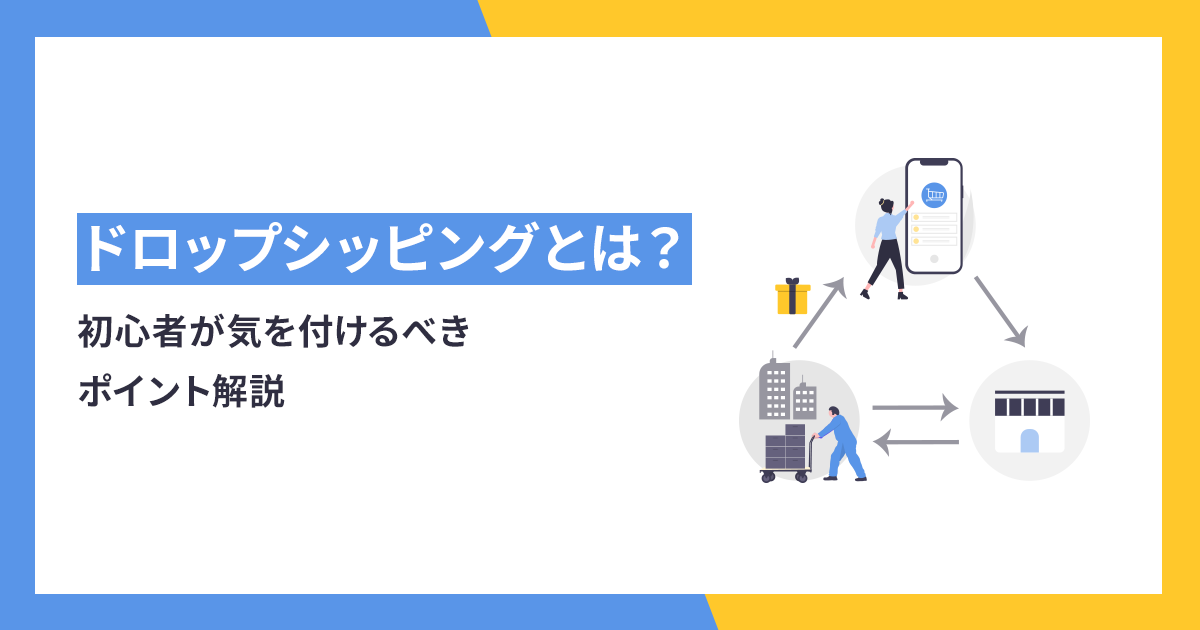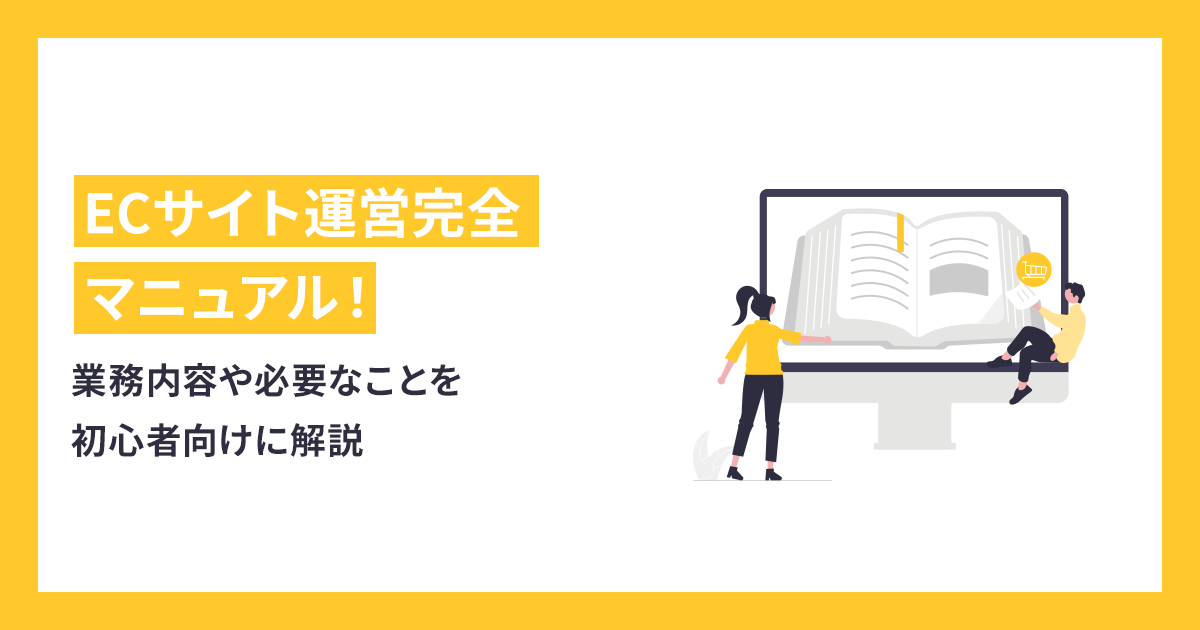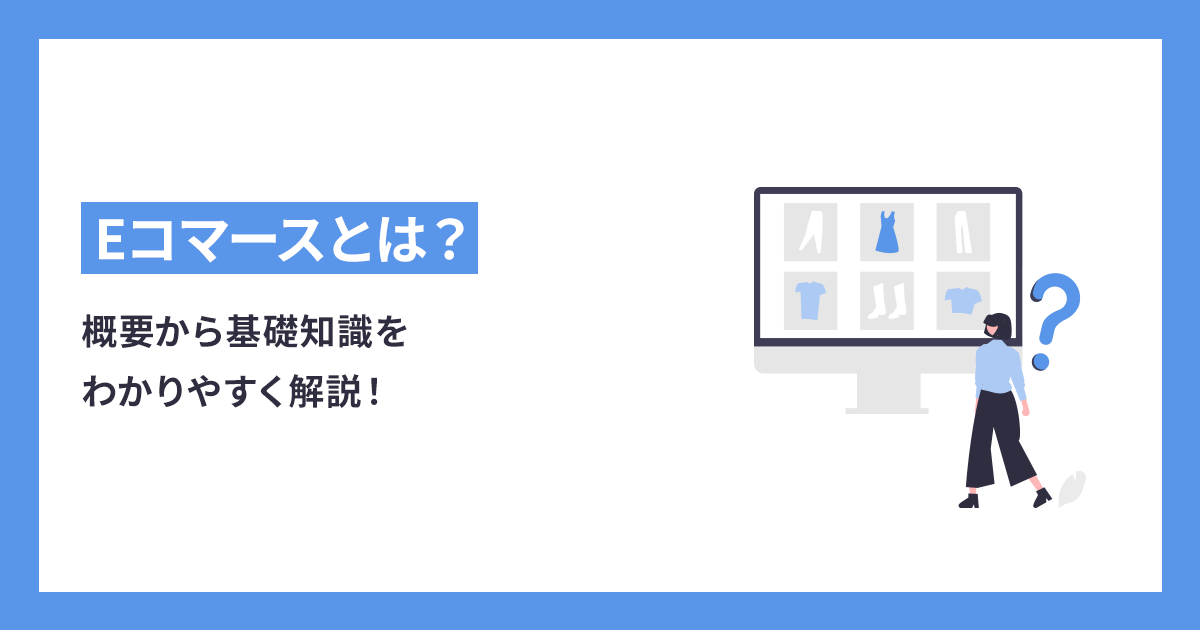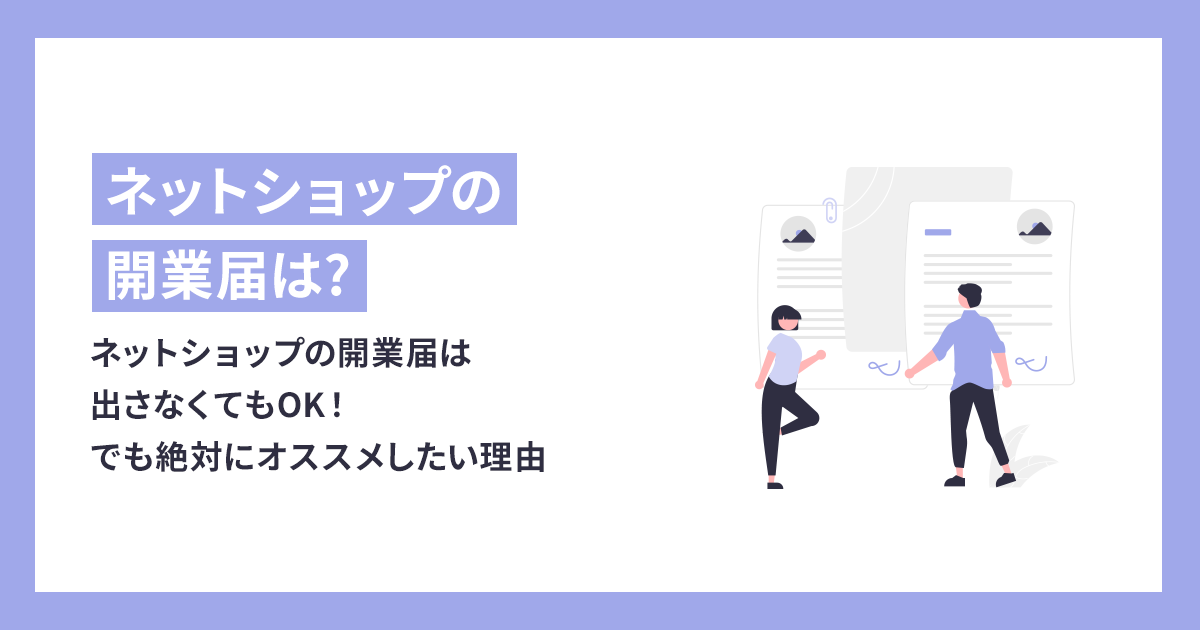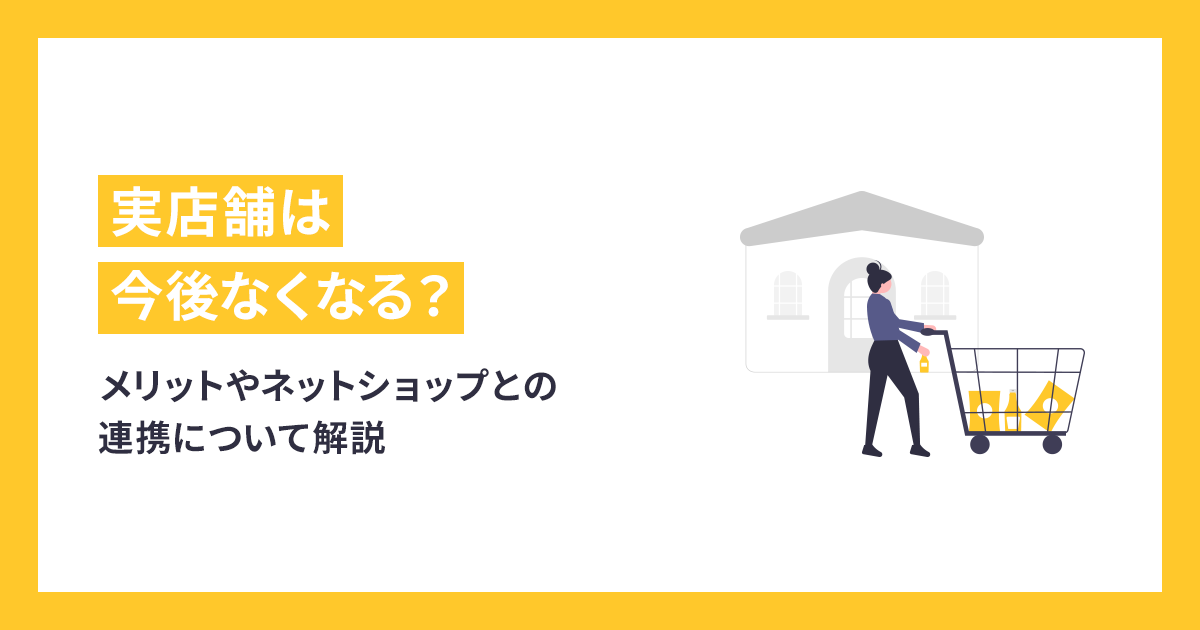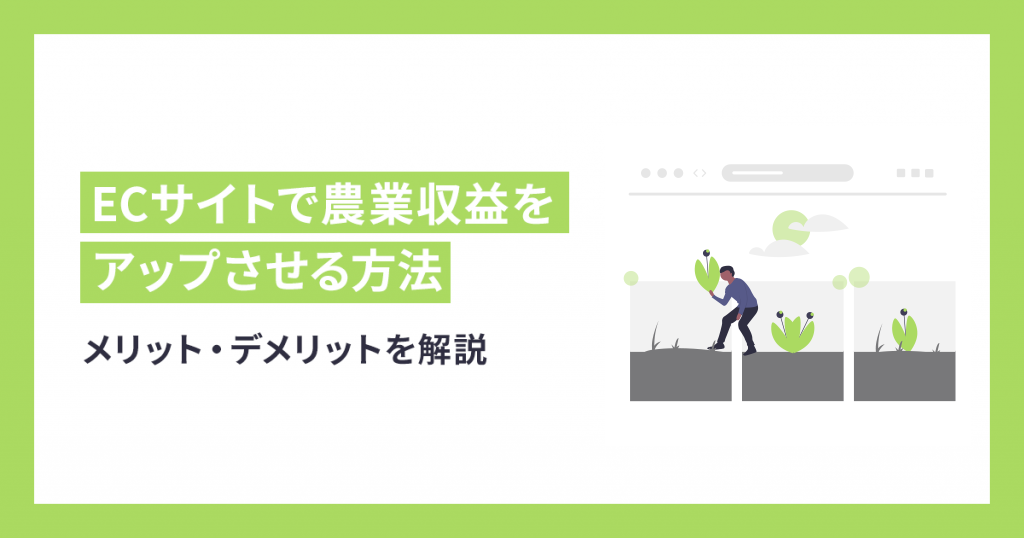
ECサイトで農業収益をアップさせる方法とメリット・デメリットを解説
農業収益をアップさせるには、作付面積を増やして「収量を増やす」のが一般的です。ただし市場へ流通させるとマージンが高く、収益性に不満を持つ方も多いかとおもいます。
収益をアップさせるには、流通の中間マージンを減らすこと。農産物直売所や道の駅で直売されている方も多いと思いますが、インターネット上にECサイトを立ち上げて、全国の消費者へ販売する方法も今注目されています。
ECサイトには多くのメリットがありますが、もちろんデメリットもあります。今回は畑作・野菜の農業経験のある筆者が、ECサイトを立ち上げる際に考えておくべきポイントを、農家目線で詳しく解説します。
ECサイトで農作物を販売する5つのメリット
農家がECサイトを立ち上げて販売するメリットは次の5つです。
- 売上・利益率アップが期待できる
- 規格外や余剰の農作物も売れる
- 定期購入サービスをはじめられる
- 鮮度の高い野菜を届けられる
- 消費者から直接感想を聞ける
ひとつずつ見ていきましょう。
1. 売上・利益率アップが期待できる
農業協同組合(JA)に出荷する場合、JA組織規模や販売ルートなどの理由で販売手数料は高くなります。中間マージンを減らして収益性を高めるには、「農産物直売所」や「道の駅」で販売する方法が一般的です。
農作物直売所の販売手数料は、委託式で10%~25%の相場。ECサイトの場合はサイトの規模や構築方法によって異なりますが、おおむね大差はありません。大きな違いはECサイトの場合、全国・世界の消費者とつながり取引できること。そして24時間365日、自動で販売できることです。地の利に関係なく、インターネットを介して販路拡大が見込めます。
2. 規格外や余剰の農作物も売れる
市場流通において、規格に適合しない農作物は「規格外」となり売れませんが、お得であれば規格外でも購入したい消費者の方はたくさんいます。ECサイトを介すことで需要と供給がマッチし、無駄なく販売し収益化できるようになります。
3. 定期購入サービスをはじめられる
農業に限らず事業収益を安定させるには、顧客の「リピーター化」 は欠かせません。ビジネスは大きくわけて「フロー型」と「ストック型」の2種類があります。フロー型は、直売所のように、新規顧客を常に獲得する売り切り型のビジネス。ストック型はファン顧客をつくりリピーター化することで、定額の収益を上げて安定させるビジネスです。
農業系のストック型ビジネスは、「らでぃっしゅぼーや」や「オイシックス」などが有名ですが、自分でECサイトを運営すれば、同類の定期便を出すこともできます。定期便はお客様の要望にもよりますが、「月に1回」や「2週間に1回」など、農作物の生産状況にあわせて配送頻度を自由に設定できます。
4. 鮮度の高い野菜を届けられる
一般的な流通では、生産者(農家)→出荷団体(農協など)→卸売市場→小売業者(スーパーなど)を経るため、鮮度が落ちるのは避けられません。消費者の中には多少値段が高くても、おいしい農作物を食べたいニーズが一定数あります。
スーパーなどで新鮮さをアピールした「朝採り野菜」が売られていますが、キャベツやほうれん草などの葉菜類は、夕方の収穫がおいしいと言われます。農産物に応じた最適なタイミングで収穫し、流通よりも短い日数で届けられることは、美味しさや鮮度を求める消費者にとって大きなメリットと言えるでしょう。
5. 消費者から直接感想を聞ける
ECサイトを介して直接お客様とつながると、さまざまな声が届きます。「野菜嫌いの子どもがおいしく食べてくれた!」という嬉しい声もあれば、商品やサービスの辛口コメントもあります。辛口のコメントは耳が痛いですが、消費者側ニーズや要望など、営農に役立つヒントが多く隠されています。
お客様の要望や指摘に真摯に向き合い改善することで独自ブランドが磨かれて、ファンがつきやすくなります。
ECサイトで農作物を販売するデメリット
つづいてECサイトの短所を見ていきましょう。
- 農作業以外の仕事量が増える
- 在庫管理に工夫が必要
- 競合するライバルが増える
- カスタマーサポートの作業が増える
ひとつずつ解説します。
1. 農作業以外の仕事量が増える
ECサイトを運営するには、さまざまな作業がともないます。ECサイトの制作・管理はもちろん、受注後の梱包や発送、お客様からの質問・問い合わせ対応など…。そしてECサイトに訪問してもらえるよう「集客」の努力もかかせません。
農作業で忙しいなら、ECサイト運営の一部~全てを任せられる代行会社も数多くあります。ただし、その分コストがかかるので、コストを支払ってもペイできるか見極めは大切です。
2. 在庫管理に工夫が必要
農作物は日照量や降水量などの気候で収穫量が大きく変わります。定期便などを販売する場合は、いつまでに・どれくらいの収量が必要かを見定めなくてはいけません。また、日持ちしない農作物は在庫をしっかり管理しないと、受注後に欠品を起こすトラブルが起きやすくなります。通年で安定した販売をするためには、乾燥処理や防腐加工など工夫が必要です。
3. 競合するライバルが増える
ECサイトの市場はお客様の母数が多い反面、ライバルとなる農家も多く存在します。特に差別化が難しいECモールの場合は、価格競争が起きやすく、「売れるけど儲けがでない」ことも珍しくありません。ECサイトで成功させるには、サービスや商品で差別化をはかり、お客様から選ばれることが大切です。また、新規顧客を獲得したあとは、丁寧なサポートでファンになってもらうことも欠かせません。
4. カスタマーサポートの作業が増える
ECサイトは一般消費者向けの取引(BtoC)がメインです。BtoCの取引は「少量・多出荷」になるため、1件あたりの作業量が多くなります。配送や商品に関する問い合わせも多く、「商品はいつ届くのか?」、「配送先を変更して欲しい」、「○○の入荷はいつごろ?」など・・・。問い合わせはメールが基本なので、農作業のスキマ時間に応対できます。が、返信が遅いと不満を感じるお客様もいます。これまでの農作業に加えてEC業務をこなせるか?難しければスタッフの雇用も考えましょう。
ECサイトで農作物を販売する際に気をつけること
ECサイトで販売するときに、抑えておきたいポイントを紹介します。
はじめは規模を小さくEC販売を行う
ECサイトを構築する方法は、カートASPやECパッケージなどの構築方法があります。オリジナル性の高いECサイトを作れば数十万円~数百万円の構築費用はかかりますが、オープンしてすぐに売れるわけではありません。集客するためには継続した労力と投資が欠かせませんが、思うように売れず、資金の底がついて撤退するケースも珍しくありません。
はじめてEC販売するなら、出品と集客がカンタンな産直ECやフリマアプリからスタートするのも良いでしょう。まずは小さくはじめてEC販売の感覚をつかみ、慣れてきたらECモールや自社ECへとステップアップすれば、失敗リスクを大きく減らせます。
損益分岐点をしっかり計算しておく
ECサイトのランニングコストは、ECカートシステムの月額料金(数千円~数万円)や、決済手数料(売上額3%~5%+契約料)がかかります。そのほか、梱包資材やスタッフの人件費、通信費など。
ECサイトで販売する際は、農作物の原価と上記コスト、そして「儲け」を加味して値付けしましょう。ライバル農家が多いと、価格競争に陥りやすいですが、儲けを減らしすぎると必ず経営が苦しくなります。事業継続が可能な損益分岐点を意識して計算しましょう。
集客方法を事前に考えておく
ECサイトはオープンしてからが勝負。最初は訪問するお客様は皆無なので、「集客」にこそ力を入れなくてはいけません。
- 口コミ(SNSなど)
- ネット広告(Yahoo!Googleなど)
- 自然検索(SEO)
最もコストを抑えて集客できるのは、InstagramやTwitterなどのSNSを活用して潜在顧客へ拡散すること。ただしフォロワーを集めるには時間と労力が必要です。集客の即効性があるのはネット広告ですが、継続的な投資は欠かせないので、資金にある程度の余裕は必要です。
法律を遵守する
農作物をそのままECサイトで販売するのであれば、販売許可や開業届はいりません。ただし、農作物を加工して「ジャムを販売したい」、「お酒を販売したい」というケースでは、営業許可や製造許可が必要です。
| 商品 | 関連する法律 | 申請する届け出 | 申請の管轄 |
| 農産物加工品 | 食品衛生法 | 営業許可 | 保健所 |
| 酒類の製造・販売 | 酒税法 | 酒類製造免許 酒類販売業免許 | 税務局 |
| 健康食品の製造・販売 | 食品衛生法 医薬品医療機器等法 薬機法 | 医薬品医療機器等法に基づく許可 | 保健所 |
| 化粧品の製造・販売 | 医薬品医療機器等法 薬機法 | 医薬部外品製造販売許可 | 保健所 |
また、ECサイトを出店する際は、販売元などを明記した「特定商取引法に基づいた表示」が必須です。カートASPなどでECサイトを構築すれば、テンプレートが用意されていますので、活用して記述しましょう。
特別栽培農産物に係る表示ガイドラインも遵守する
特別栽培農作物とは、農薬や化学肥料の使用量が通常以下の量で栽培された農作物のことです。ライバル農家と差別化をはかるためにも、「無農薬」や「減農薬」をアピールしたいところですが、国内で販売する際はNGワードとなります。
農薬を全く使用しない場合は、「農薬:栽培期間中不使用」。節減対象でない農薬を使用した場合は「節減対象農薬:栽培期間中不使用」など、農林水産省のガイドラインにそって正しく記載しましょう。なお、現状はフリマアプリを中心に、ガイドラインに違反した出品が多く見られます。ガイドライン上の罰則はありませんが、不当表示とみなされれば、景品表示法違反や不正競争防止法違反となり、罰則や損害賠償請求される可能性もあります。
まとめ
今回は、農作物をECサイトで販売するポイントを紹介しました。ECモールや産直ECを活用すれば比較的カンタンに出品できますが、ライバル農家と価格競争に陥りやすく、「売れても儲からない」ケースはよく見受けられます。
中・長期にわたりEC販売を成功させるには、ライバルに負けないブランド力が求められます。ブランドは商品・サービスの品質だけではなく、高評価レビューの件数やファンの多さなどの「無形資産」を築くことも大切。「〇〇円儲けるためにはどのようなブランドを作り上げるべきか?」の視点で戦略を立てましょう。