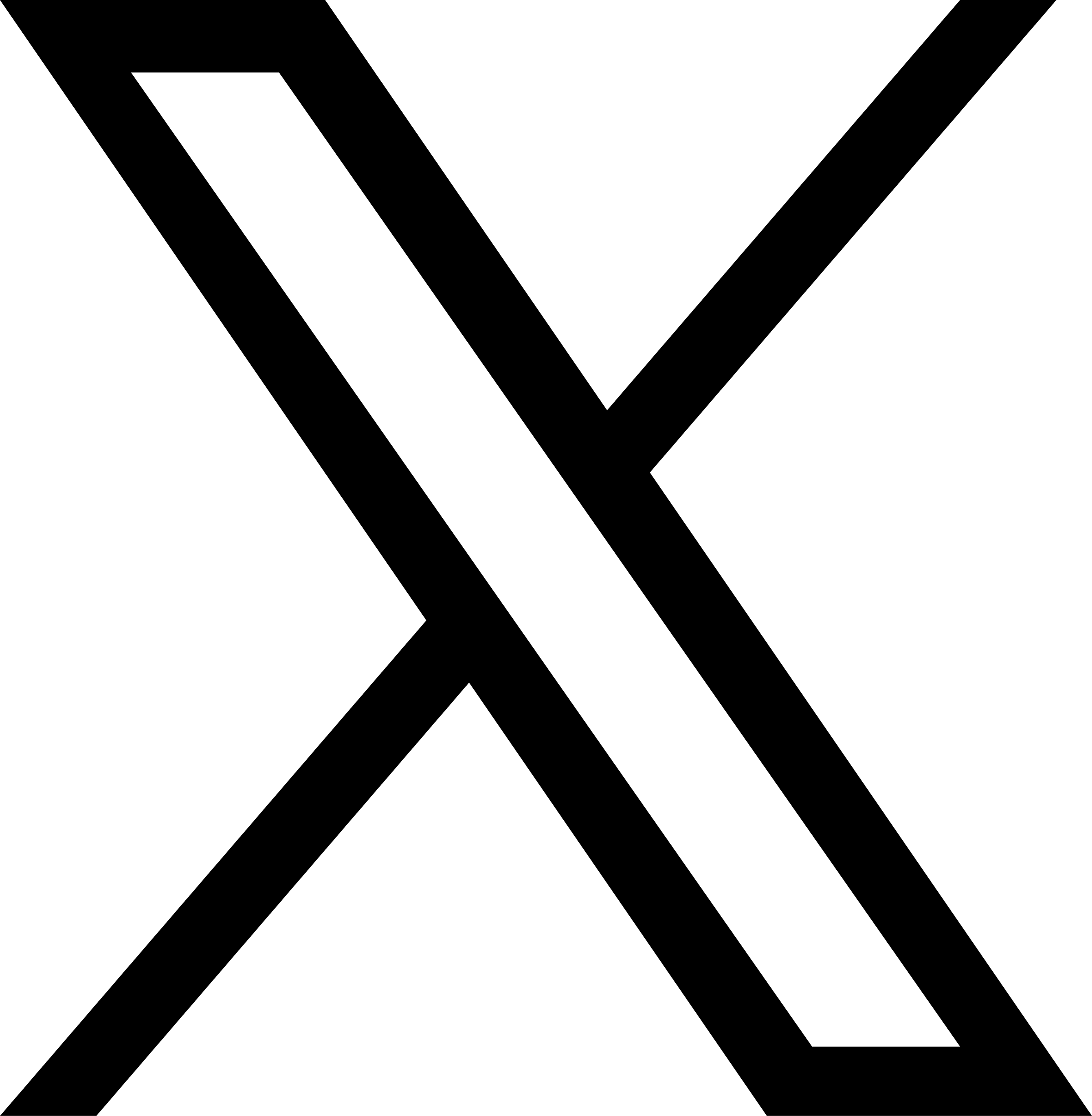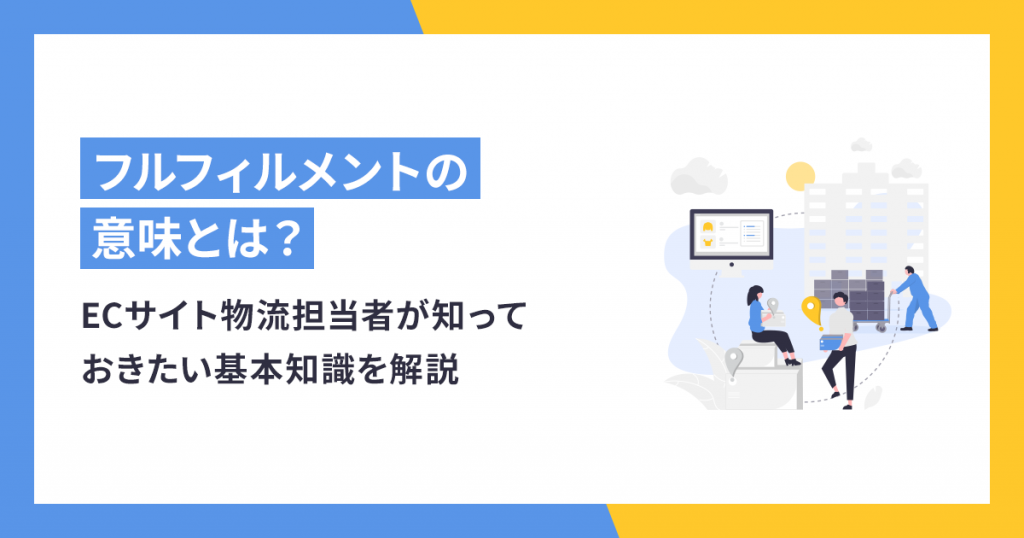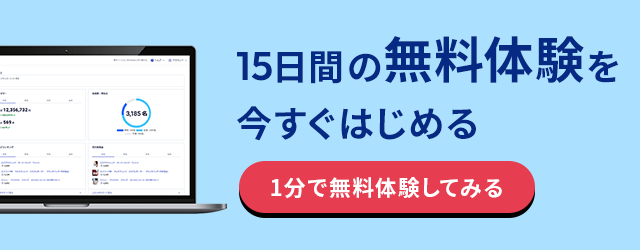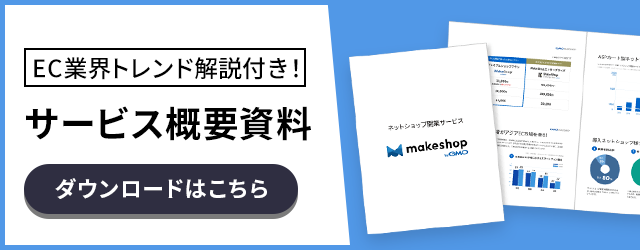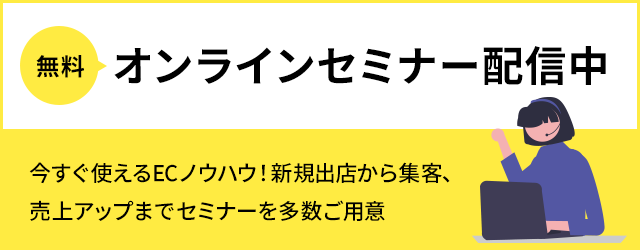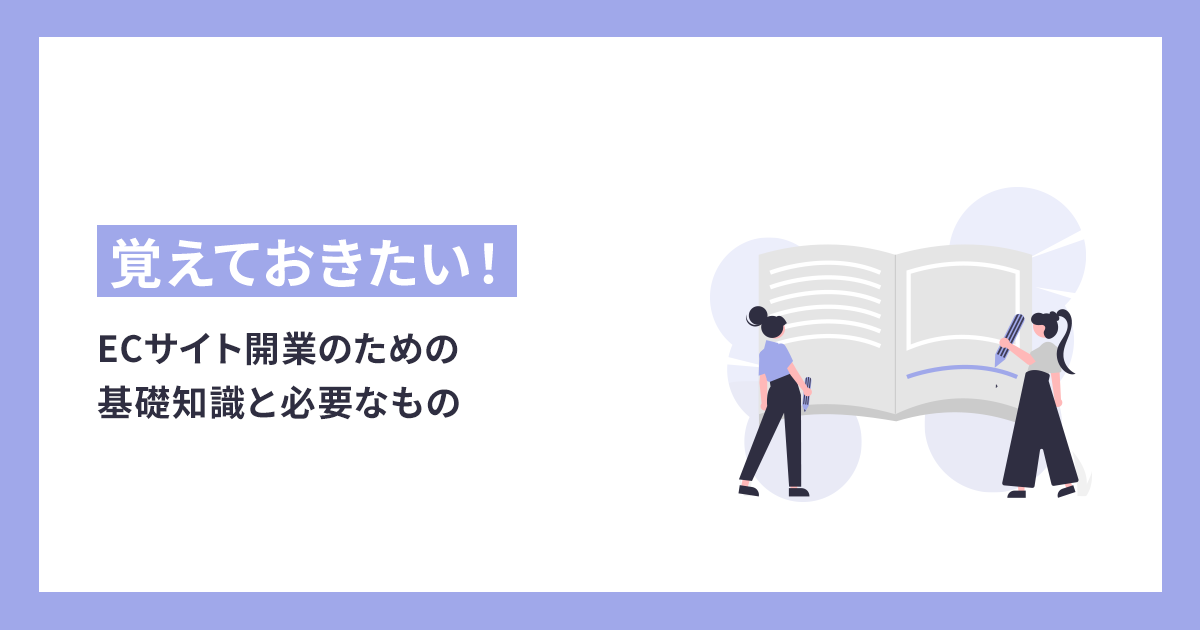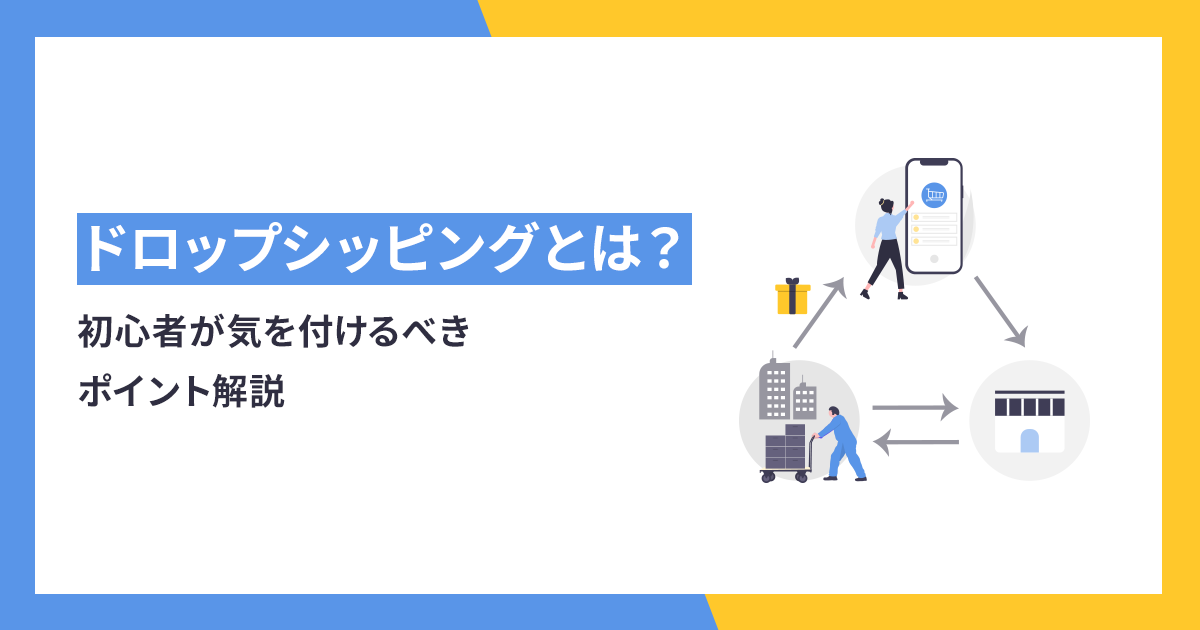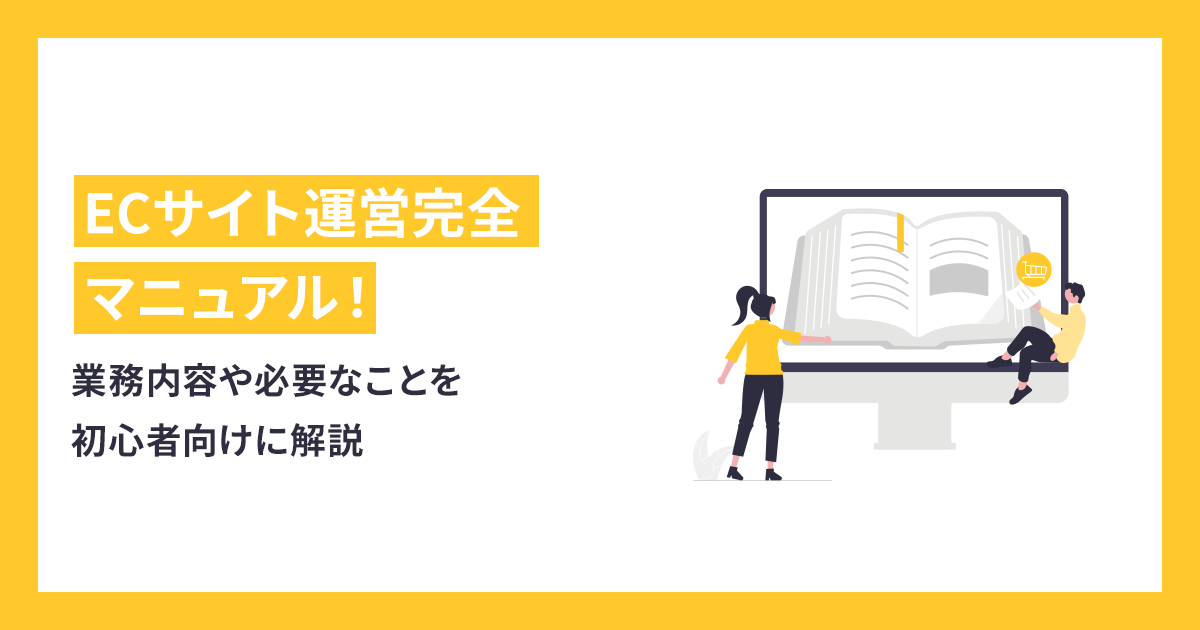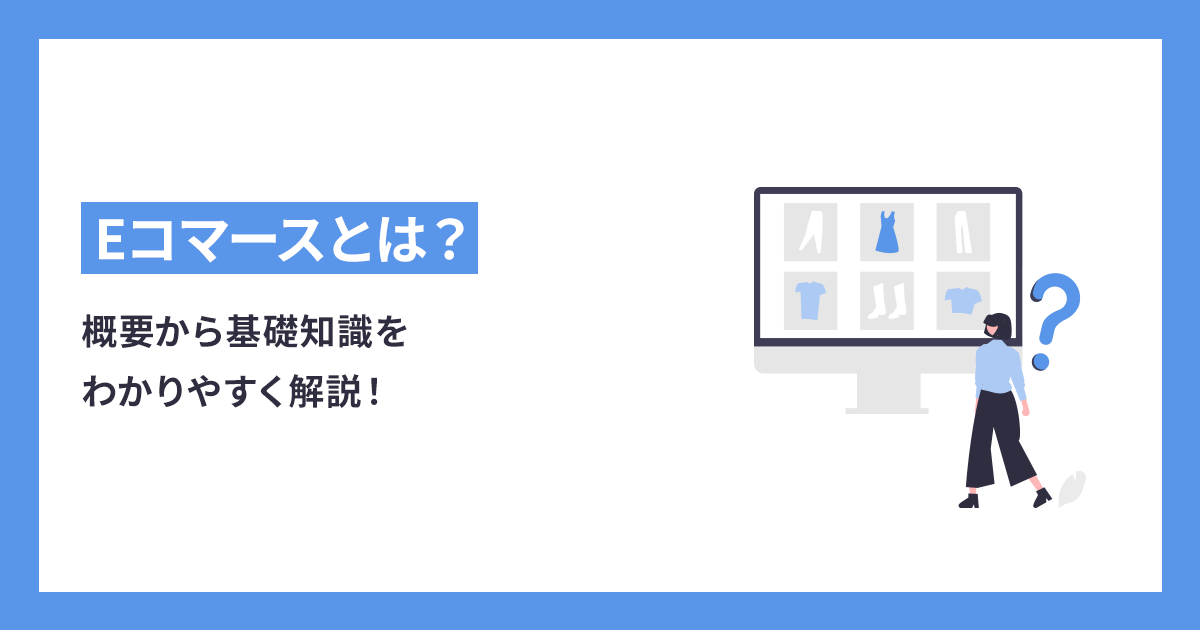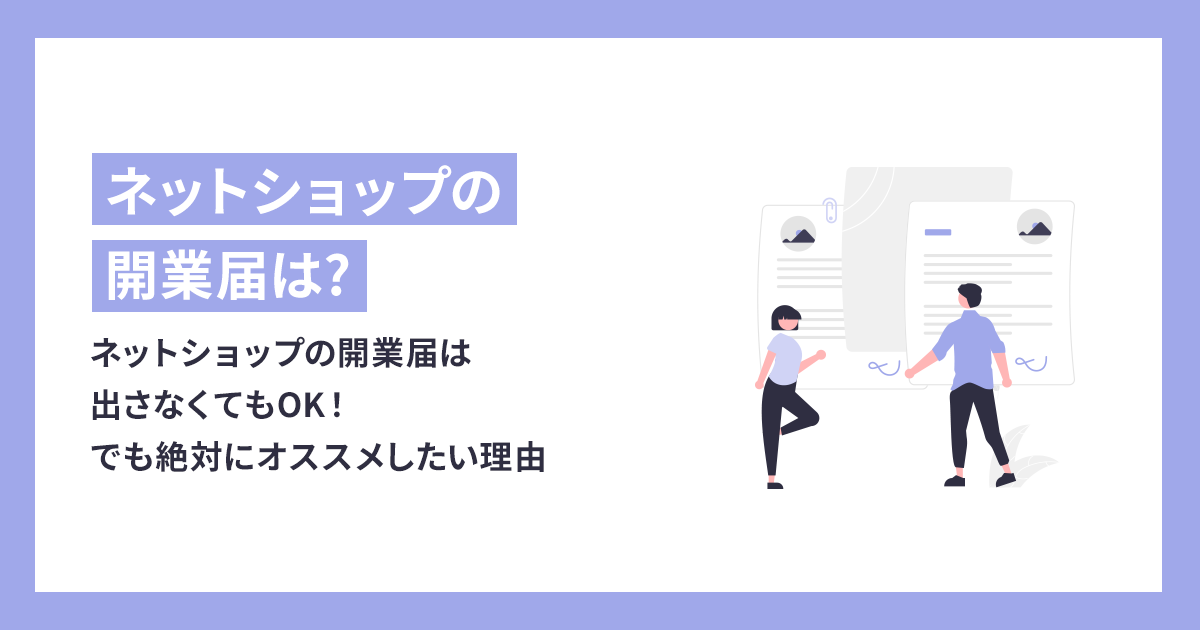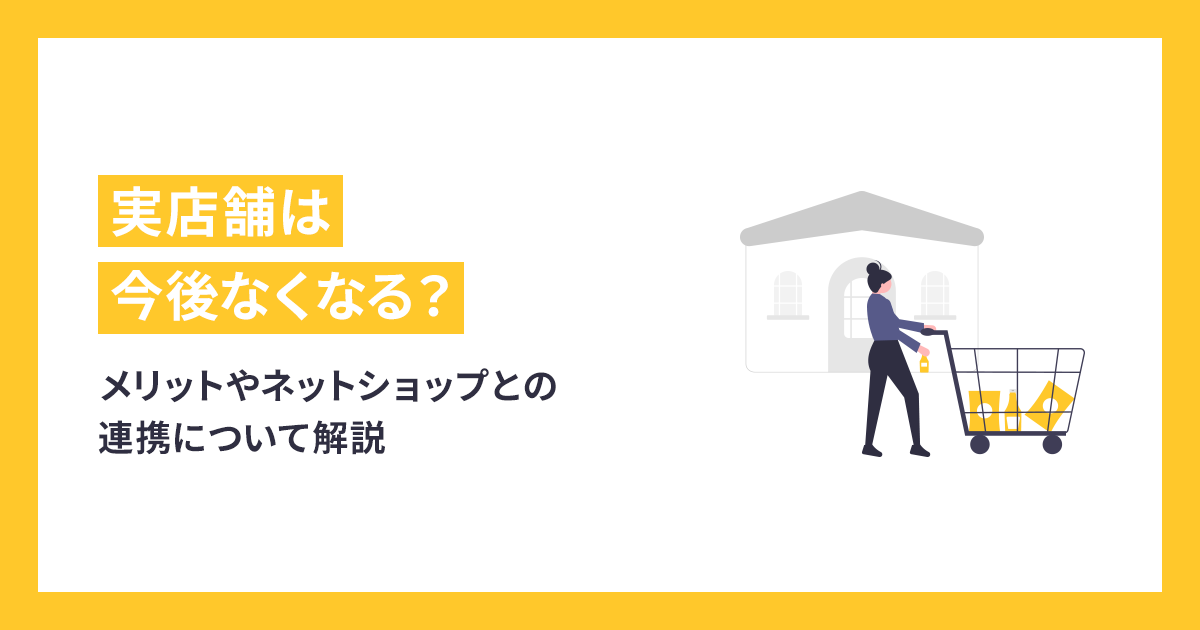AIDMA (アイドマ)の法則は代表的な消費行動モデル!古すぎる?
AIDMA(アイドマ)は、消費行動のステップを表したフレームワークのひとつです。AIDMAモデルは100年以上前に提唱された法則ですが、時代の変化とともに新しいモデルが続々と登場しています。今回はAIDMAを詳しく解説するとともに、新しいフレームワークについて詳しくふれます。最後までご一読ください。
アイドマ(AIDMA)は100年前のフレームワーク
AIDMAは、消費者が商品やサービスを購入するにいたるまでの流れを表したモデルです。消費者が行動するステップの頭文字をとってAIDMA(アイドマ)と名付けられています。
- A→Attention(注意・認識)
- I→Interest(興味・関心)
- D→Desire(欲求)
- M→Memory(記憶)
- A→Action(購買)
消費者は見ず知らずの商品やサービスに対してAttention(注意・認識)からはじまり、最終的にAction(購買)へいたるステップをたどります。それぞれのステップを分割することで、消費者がいまどの段階にいるのかが分かるようになります。
次の章でさらに詳しく解説します。
AIDMAの理論は「認知」「感情」「行動」の3つがある
AIDMAを構成する行動は、次の3つに分類できます。
- 認知→Attention(注意・認識)
- 感情→Interest(興味・関心)、Desire(欲求)、Memory(記憶)
- 行動→Action(購入)
最初の「認知」は、あなたの商品やサービスを全く知らない消費者が、はじめて存在を知る段階です。次の「感情」は、あなたの商品やサービスを認知したときに、”好き”か”嫌い”を判断する段階。最後の「行動」は、感情によって購入するかしないかを判断する段階です。
消費者が購入までいたるには、商品やサービスの好感度を上げることが大切。「好感度」という感情を上げるには、商品やサービスを理解してもらい潜在的なニーズを促すこと。そして忘れないように接触をふやすことです。それぞれの行動プロセスを詳しく掘り下げてみましょう。
Attention(注意・認識)
Attentionは、商品やサービスのことを「まだ知らない」段階です。世の中にはたくさんの商品やサービスが溢れていますよね。その中で、あなたが販売する商品やサービスに注目してもらうことが、最初のステップです。
- 広告(テレビ、ラジオ、新聞、ネット)
- 対面営業
- 口コミ
- SNS
- 検索(Googlenなど)
- メディア記事
主に上記のメディアを活用しAttentionを行います。なお、AIDMAが登場した100年前のメディアは、ラジオ、新聞と口コミです。新聞は1870年代に登場し、ラジオは1920年代から広まりました。インターネットが登場した1990年代以降は、情報量が格段に増えました。時代とともにメディアは変化しますが、Attentionにおいての目標は「認知度の向上」で変わりありません。
Interest(関心)
Interestは、商品やサービスのことを「知っているけど興味がない」段階。そしてInterestにおける目標は「評価の育成」です。消費者に対して商品やサービスに関心をもってもらうには、「自分に関係のある話だ」と認識してもらうこと。言いかえると「自分にとってメリットがある話」をすれば、関心を得ることができます。メリットは相手の立場や属性によって異なります。しっかり見極めて訴求することで共感を得やすくなります。
Desire(欲求)
Desireは、商品やサービスのことを「興味はあるけど欲しいと思わない」段階。そしてDesireにおける目標は「需要の喚起」です。消費者の興味・関心の度合いは大きく分けると「潜在層」、「準顕在層」、「顕在層」の3パターンに分けられます。
顕在層は自分の興味・関心が明確ではない層。まずは「知ってもらう」Attentionの段階です。準顕在層は、興味・関心が明確だけど、買う気の無い層です。Desireの段階においては、この準顕在層に対して購入の意欲を高めてもらうことに努めます。
Memory(記憶)
Memoryは、商品やサービスのことを「欲しいと思ったけど忘れている」段階。Memoryにおける目標は「記憶の呼び起こし」です。準顕在層の購入意欲を保つのはとても困難です。それほど意欲的でなければ、購入を後回しにしてしまい…記憶から排除されてしまいます。人間の脳は効率的にできており、無駄な情報や無意味なモノを排除するようにできています。つまり意識して記憶を保たせないと、忘れてしまい購入には至らないのです。
購入意欲が高くても、いますぐに購入しないでセールのタイミングをはかっていたり、何かのついでに購入しようと考えていたりもします。いずれの場合も時間が経ちすぎると忘れやすくなる点に注意が必要です。
Action(行動)
Actionは、商品やサービスのことを「動機はあるけど購入機会がない」段階。Actionにおける目標は「購入機会の提供」です。リアル店舗であれば、全国に数カ所しかないお店よりも、コンビニのように近所で購入できることが購入機会の提供につながります。ECサイトの場合、スマホがあればいつでも購入機会を提供できますが、消費者が望むサービスが無いと購入機会を失います。例えば、急ぎで届けてほしい消費者は「即日配送」が購入機会になります。クレジットカードを持たない消費者であれば、コンビニ決済や代金引換などの提供が購入機会の提供になります。
AIDMAモデルを活用する3つのメリット
販促活動において、AIDMAを活用するメリットは次の3つです。
- ユーザーの心理状態にあわせたマーケティングができる
- 自社の弱みや課題を明確にできる
- 最適なペルソナマーケティングを実施できる
ひとつずつ詳しく解説します。
ユーザーの心理状態にあわせたマーケティングができる
消費者の興味・関心の度合いは「潜在層」、「準顕在層」、「顕在層」の3パターンあるとお話しました。消費者の心理状態に応じて必要な施策は異なり、間違った施策を訴求しても刺さりません。刺さらないことに営業の時間を投じても無駄が大きいですし、広告費をかけてもコストパフォーマンスは優れません。それぞれのステップに応じて、やるべきマーケティング施策は明確になります。
自社の弱みや課題を明確にできる
例えばAction(購入)のステップにおいて、思うように購入へ結びつかないケースがあります。購入意欲が高くても売れない理由は、消費やサービスの質が問題とは限らず、ライバル企業より品質やサービスが劣っている可能性も考えられるでしょう。ステップに応じて期待通りの成果がでない理由は必ずあります。社内の弱みを改善することで成果に結びつきます。
最適なペルソナマーケティングを実施できる
ペルソナマーケティングとは、自社の商品やサービスを購入してくれる消費者(ペルソナ)を具体的に設定し、消費者の行動や思考を分析する手法です。例えば骨董品を販売しているなら、ユーザーは「中高年」「男性」「高年収」というペルソナが設定できます。
ペルソナを深堀することで、AIDMAの各フェーズにおいて効果的な施策を打つことができます。骨董品を例にあげると、中高年の男性がよく利用する新聞や雑誌に広告を出せば高い成果を期待できますが、若年層ユーザーが多いInstagramに広告を出しても成果は出づらいでしょう。ペルソナの年齢や性別、職業、年収を設定することで、普段どのような生活を送りどんな悩みを持っているかが想像しやすくなります。
AIDMAのテンプレートと具体例
あなたのお店がシューズ専門店だった場合を例に、AIDMAテンプレートの事例を紹介します。
| Attention(注意・認識) | Interest(興味・関心) | Desire(欲求) | Memory(記憶) | Action(購買) | |
| ユーザーの状態 | SNSでバズっているシューズを発見する | モデルの投稿をみてコーディネートをチェックする | 口コミや価格を検索し比較する | リマインダー登録してセールを待つ | 購入する |
| 目標 | 広告で認知度を増やす | 高評価レビューを増やす | 競合よりサービス・価格に優位性をとる | リターゲティング広告やメルマガを配信する | クーポン配布などでリピーター施策を行う |
| 接触ポイント | SNS | SNS | ECサイト 店舗 | ネット広告 メール | ECサイト 店舗 |
このようにAIDMAのステップに応じて「ユーザーの状態」、「目標」、「接触ポイント」を記述します。最終的なゴールである「購買」にいたるまでのカスタマージャーニーと、どのステップで何をすべきかよくわかるかとおもいます。また、チーム内や上司、クライアントへ報告する際も、わかりやすく伝えることができます。
「AIDMA」と「AISAS」の違い
AIDMAが誕生したのは1920年代。当時の消費者が情報を得られる手段は新聞やラジオ、そして対面営業に限られていました。時はたち現代はネット社会。消費者の購買行動も変化し「AISAS」モデルが注目されるようになりました。AISASモデルはつぎのとおりです。
- Attention→注意・認知
- Interest→興味・関心
- Search→検索
- Action→購買
- Share→共有
AIDMAとAISASは、Attention(注意・認知)、Interest(興味・関心)までは同じステップを踏みます。違いはAIDMAがDesire(欲求)→Memory(記憶)するのに対して、AISASではSearch(検索)へと続く点です。
Search(検索)はみなさんお馴染みのとおり、Yahoo!やGoogleで検索したり、SNSで口コミを確認したりする行動です。とくにスマートフォンが登場してからはネットとの距離が格段に近くなりました。場所を選ばず通勤・通学時や休憩中、デート中など興味を持ったらすぐに行動できるのが特徴です。
また、AISASの特徴はShare(共有)にあります。AIDMAの時代は家族や知人など限られた人にしか商品・サービスの口コミは共有されませんでした。AISASではLINEやSNSなどを活用して、より広範囲の人へ共有されます。高評価の口コミは新たな購買を呼びますが、低評価だと購買意欲が低くなります。
Dual AISAS(デュアル・アイサス)とは
Dual AISASは、「共有したい」「拡散したい」「バズらせたい」というユーザーのシェア心理に特化したモデルです。従来のAISASは購買にアンテナをはる(Attention)ユーザーでしたが、Dual AISASは広めたい(Active)にフォーカスする点に特徴があります。
- AISAS→「Attention(買いたい)」+「ISAS」
- Dual AISAS→「Active(広めたい)」+「ISAS」
Dual AISASにおいて、ユーザーは商品やサービスに興味・関心があるわけではありませんし、重要視されません。面白いコンテンツ、感動できるコンテンツなどを通じて「拡散しコミュニケーションする」ことに関心があります。
Dual AISASは直接的に購買につながるモデルではないので企業にとってメリットが無いように思うかもしれません。しかしボリュームが最も多い潜在層に対してAttention(注意・認識)を得られれば、次のステップでAISASにつなげることが期待できます。
なお、Dual AISASにおいて拡散を得やすいポイントは「無料サービス」や「○ヶ月間無料お試しキャンペーン」など。ユーザーにとって心理的ハードルが低いキャンペーンを用意することで、購買へとつなげやすくなります。
AIDMAだけじゃない!オススメの購買行動モデル
消費者の購買行動モデルは時代とともに変化しています。「AIDMAと似ているマスメディア時代のフレームワークは次のとおりです。
| モデル名 | 読み方 | プロセスの流れ | 内容 |
| AIDA | アイダ | Attention(注意) Interest(興味・関心) Desire(欲求) Action(購買行動) | AIDMAの原型となったモデル。消費者の行動を把握するために活用される。 |
| AIDCA | アイドカ | Attention(注意) Interest(興味・関心) Desire(欲求) Conviction(確信) Action(購買行動) | AIDAモデルにConviction(確信)が加えられたモデル。主にダイレクトマーケティングで活用される。 |
| AIDEES | アイデス | Attention(注意) Interest(興味・関心) Desire(欲求) Experience(体験) Enthusiasm(熱中) Sharing(共有) | 消費者が商品の認知から購買に至るまでのプロセス。購入後の口コミやSNSなどの共有を重視する。 |
| AISCES | アイシーズ・アイセアス | Attention(注意) Interest(興味・関心) Search(検索) Comparison(比較) Examination(検討) Action(行動) Share(共有) | AISASに比較・検討のプロセスが加えられたモデル。 |
| ARCAS | アルカス | Attention(注意) Remind(思い起こし) Compare(比較) Action(購買) Satisfy(満足) | 店頭などでリピート購入してもらうためのモデル。実際に商品やサービスにふれて思い出す一連のプロセス。 |
| AMTUL | アムツール | Awareness(認知) Memory(記憶) Trial(試用) Usage(本格的使用) Loyalty(愛用) | まずは試用(Trial)からはじまり、日常的に購入(Usage)しロイヤルカスタマーへと顧客育成を考慮した態度変容モデル。 |
いずれのフレームワークも、AIDMAやAISASがベースとなり変化をとげています。
インターネット社会の購買行動モデル
インターネットが普及してからは、消費者の購買モデルも大きく変わりました。ネット社会の代表的な購買モデルは次のとおりです。
| 名称 | 読み方 | 略称 | 内容 |
| SIPS | シップス | Sympathize(共感する) Identify(確認する) Participate(参加する) Share&Spread(共有・拡散する) | 共有や拡散を想定したソーシャルメディアに対応した購買行動モデル |
| DECAX | デキャックス | Discovery(発見) Engage(関係構築) Check(確認) Action(行動) eXperience(体験) | オウンドメディアやウェビナーなどのコンテンツマーケティングに対応した購買行動モデル |
| VASAS | ヴィサス | Viral (口コミ) Influence (影響) Sympathy (共感) Action (行動) Share(共有) | SNSやインフルエンサーを通じた口コミから消費者が行動するモデル |
ネット社会がもたらしたShare(共有)は、単に商品やサービスを購入して保有するモデルにとどまらず、フリマやレンタカーのようなシェアリングエコノミーを生み出しました。インターネットのプラットフォームを介して、より多くの人と共有して利用する新しい経済の形。経済活動をモデリングしたのが上記のフレームワークと言えるでしょう。
まとめ
AIDMAは商材やサービスを問わずあらゆるシーンで活用されてきました。インターネットが普及してから消費者の購買行動は変化し、それにつれて日々モデルもアップデートされています。自社が経済活動を行う市場において、マッチするモデルを活用することが大切です。AIDMAを起点に、これまでの購買行動の歴史を振り返ることで、より深みのある施策が考えられるようになるでしょう。